三浦綾子『塩狩峠』(新潮文庫)
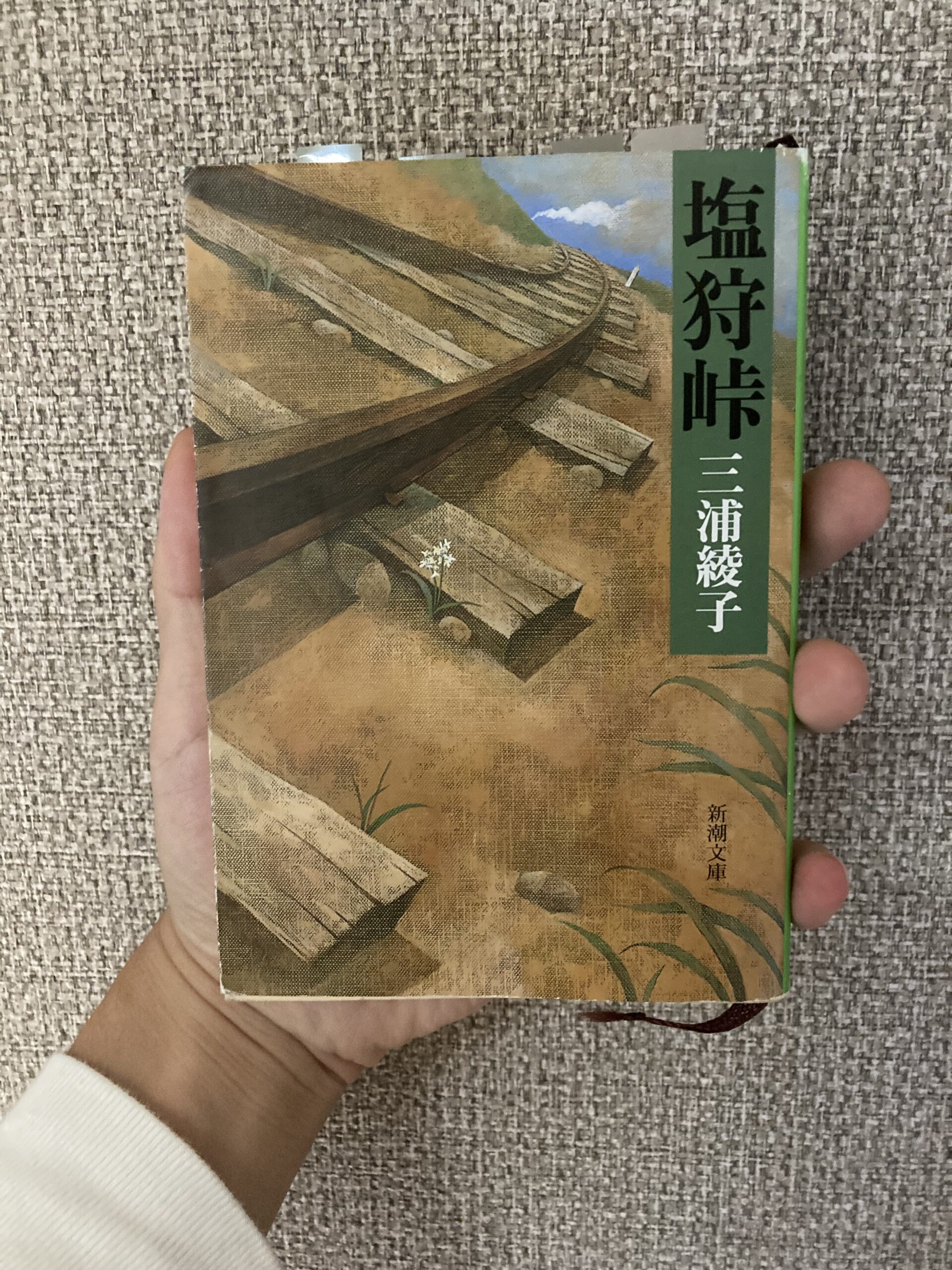
・おれは自分の日常がすなわち遺言であるような、そんなたしかな生き方をすることができるだろうか。
・あたりまえに見えていたものが、いったんふしぎになるとすべてのものが新たな関心を呼んだ。
(花ばかりじゃない。朝が来て一日があり、そして夜が来る。このことだって決してあたりまえではないのだ。宇宙のどこかには、一年中夜の所もあれば、一日中ひるの所もあるにちがいない。いや、この地上にだって、薄暮のような場所があるのではないか)
信夫はとりとめもなくそんなことを考えていた。
(第一、この自分はいったいどこから来たんだろう。)
・「そうだね。いっさいを無意味だといえばそれまでだが、ぼくはすべての言葉を意味深く感じとって生きていきたいと思うよ。君のおとうさんの死だって、僕の父のあの突然の死だって、残されたぼくたちが意味深く受け止めて生きていく時に、ほんとうの意味で、死んだ人の命が、このぼくたちの中で、生きているといえるのではないだろうか」
・「一粒の麦、地に落ちて死なずば、唯一つにてあらん」

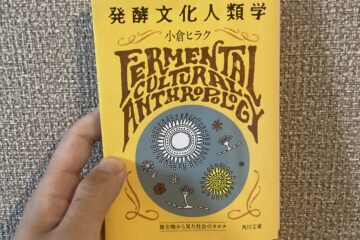
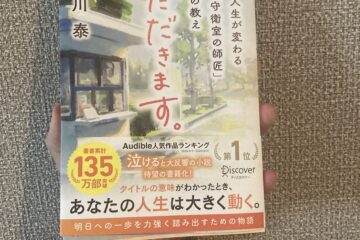
0件のコメント